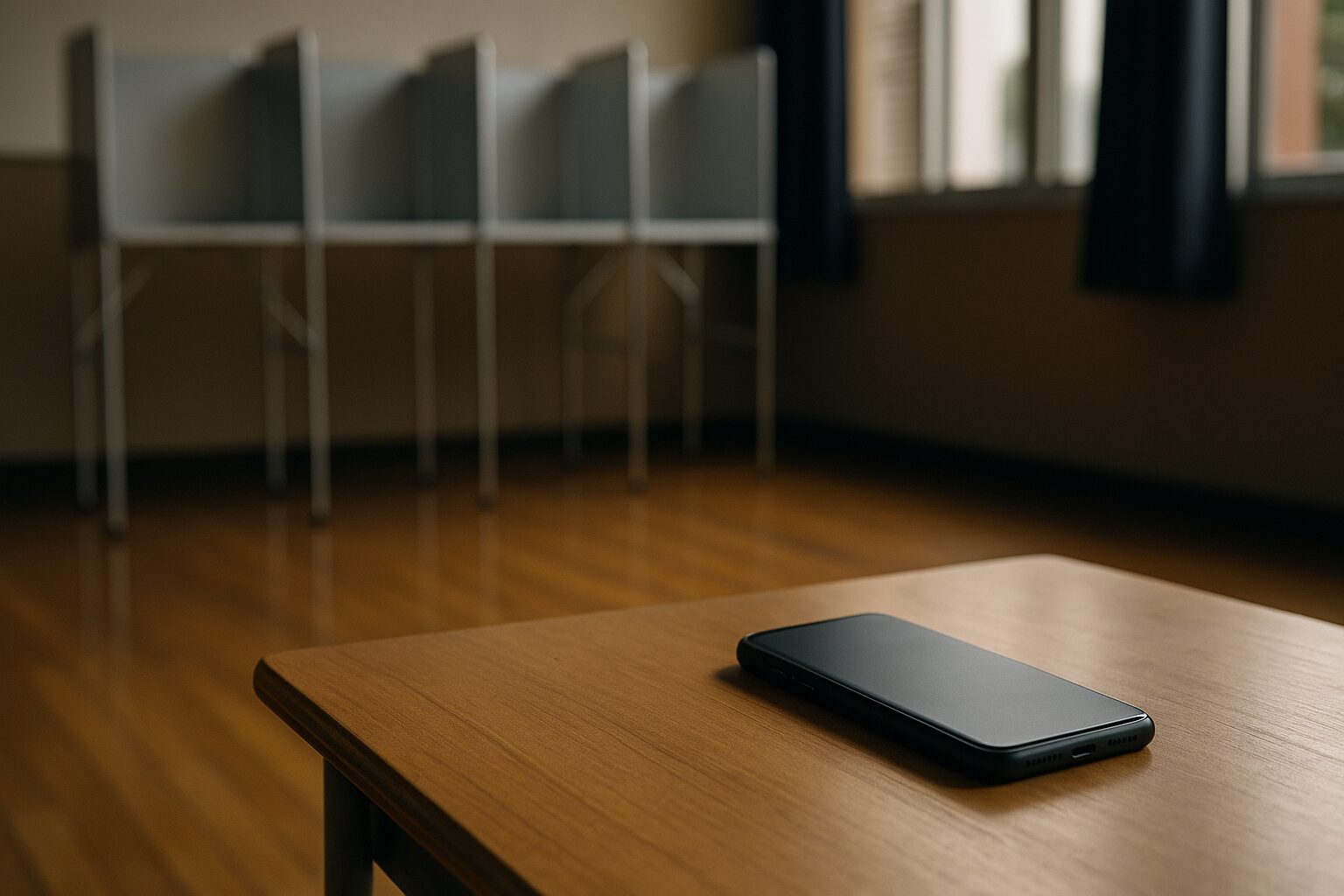インターネットを活用した選挙運動が一般的になりましたが、実は「やってはいけないこと」も数多く定められています。SNSやメールを通じて気軽に情報を発信できる一方で、知らずに公職選挙法に触れてしまうケースも少なくありません。
この記事では、「ネット選挙運動でやってはいけないこと」を中心に、禁止行為の内容や注意すべきタイミング、SNSでの具体的なリスクなどを整理します。候補者や有権者の立場に関わらず、安全に政治参加を行うための基本を確認しておきましょう。
ネット選挙運動でやってはいけないことの全体像
まず、ネット選挙運動に関する基本的な考え方を整理しておきましょう。インターネットを使った選挙運動は2013年の法改正によって解禁されましたが、すべてが自由になったわけではありません。特定の期間や方法に制限があり、違反すると罰則の対象になります。
何が「選挙運動」に当たるのか(基本の定義)
「選挙運動」とは、特定の候補者を当選させる目的で行う活動を指します。単に政治的な意見を述べることは「政治活動」ですが、誰かの当選を意図する場合は「選挙運動」とみなされます。この区別が非常に重要で、SNS上で「○○さんを応援しよう」と投稿する行為も選挙運動と判断される場合があります。
期間とタイムラインで変わる禁止行為
選挙運動ができるのは、公示(国政選挙)または告示(地方選挙)の日から投票日前日までです。それ以前や当日に特定候補への支持を表明すると、たとえSNSでも違反とされることがあります。例えば、投票日当日に「○○候補に投票しました」と投稿するのはNGです。
やってはいけない人・できる人(18歳未満や国外在住など)
公職選挙法では、18歳未満の人による選挙運動が禁止されています。また、外国籍の人も原則として選挙運動はできません。これらの制限は、選挙の公正を保つためのものです。SNSでの「いいね」や「リポスト」なども、運動と見なされる可能性があるため注意が必要です。
手段別のNGの整理(SNS・メール・広告・当日更新)
SNS投稿、メール送信、ウェブ広告など、使う手段によってルールが異なります。特にメールは候補者や政党しか選挙運動に使えません。また、投票日当日のホームページ更新やSNS投稿は禁止されています。事前予約投稿も違反と判断されるおそれがあります。
違反時の影響(罰則・当選無効・信用失墜)
違反行為を行った場合、候補者本人はもちろん、支援者にも罰則が科されることがあります。内容によっては当選が無効になることもあり、政治的信用にも大きな傷がつきます。したがって、「知らなかった」では済まされない点に注意しましょう。
・SNSの投稿も選挙運動とみなされる場合がある
・18歳未満・外国籍の人は選挙運動禁止
・メールでの選挙運動は候補者・政党のみ可
・投票日当日の更新は禁止
・違反すると罰則や当選無効の可能性あり
具体例:例えば、選挙期間中に「○○候補を応援しています。皆さんも投票しましょう」とX(旧Twitter)に投稿した場合、本人が候補者でなければ違反となる可能性があります。特に当日や前日の投稿は注意が必要です。
- 選挙運動と政治活動の区別を理解する
- 期間と手段によってルールが異なる
- 年齢や国籍で制限があることを把握する
- 違反は罰則や当選無効の対象となる
- 投稿・更新のタイミングに特に注意する
時期別に見るNG行為:公示前・選挙期間中・投票日当日
次に、時期ごとに異なる「やってはいけない行為」を整理します。ネット上では投稿の履歴が残るため、「いつ投稿したか」が重要です。公示前と選挙期間中、投票日当日ではルールが大きく異なります。
公示・告示前に控えるべき発信と注意点
公示前に特定の候補者を推す発言を行うことは、実質的な選挙運動とみなされることがあります。例えば、「次の選挙では○○さんに頑張ってほしい」といった投稿です。選挙期間が始まるまでは、個人の支持表明も慎重に扱う必要があります。
選挙期間中に禁止される行為の具体例
選挙期間中でも、やってはいけない行為は少なくありません。虚偽情報の拡散、相手候補への誹謗中傷、匿名での印象操作投稿などは明確な違反です。また、無断で候補者の写真や動画を編集・拡散することも問題になります。正確性と公正性を最優先にしましょう。
投票日当日の更新・呼びかけが禁じられる理由
投票日当日に選挙運動を行うと、投票行動に不当な影響を与えるおそれがあるため禁止されています。「投票しました」「○○候補がんばれ」などの投稿も該当する場合があります。自動投稿設定が残っていないか、前日に必ず確認しましょう。
期日前投票期間の留意点と誤解しやすいポイント
期日前投票期間中は選挙運動が許されていますが、他人に「投票しよう」と呼びかける表現は注意が必要です。また、「投票所に行ってきました」との投稿は問題ありませんが、「○○に投票した」はNGです。内容の線引きを理解して発信することが大切です。
選挙後の発信で気をつけること
選挙が終わった後も、結果に対して過度な批判や虚偽情報を拡散するのは避けましょう。選挙後は「政治活動」として意見を述べることは自由ですが、名誉毀損や風説の流布にあたる投稿には注意が必要です。
| 時期 | やってはいけない行為 | 主な理由 |
|---|---|---|
| 公示前 | 特定候補の応援投稿 | 事前運動とみなされるため |
| 選挙期間中 | 誹謗中傷・虚偽情報 | 公職選挙法第142条違反 |
| 投票日当日 | 投票呼びかけ投稿 | 当日運動の禁止(第129条) |
| 選挙後 | 結果への虚偽投稿 | 名誉毀損・業務妨害に該当の恐れ |
具体例:選挙当日に「○○候補に入れました!みんなも!」とInstagramに投稿した場合、明確な選挙運動と見なされます。仮に本人が意図していなくても、法的には違反の可能性があります。
- 投稿のタイミングで合法・違法が変わる
- 投票日当日の呼びかけは禁止
- 期日前投票中も内容に注意が必要
- 虚偽情報や誹謗中傷は常に違反
- 選挙後も冷静な発信を心がける
SNS・動画・ライブ配信でやってはいけないこと
近年はSNSを使った発信や動画配信が中心的な選挙運動の手段になっています。しかし、使い方を誤ると公職選挙法に触れるリスクがあります。特に、誹謗中傷やなりすまし行為、誤情報の拡散は罰則の対象になり得るため、投稿前に内容を慎重に確認することが必要です。
誹謗中傷・虚偽情報の拡散リスクと線引き
候補者や政党に対して事実でない内容を投稿・共有することは、名誉毀損罪や公職選挙法違反につながります。「噂を聞いた」「誰かが言っていた」といった不確かな情報を拡散するのも危険です。批判をする場合でも、根拠のあるデータや公的情報に基づいて発言することが求められます。
なりすまし・偽装アカウントの禁止と見破り方
他人の名前や写真を使ってアカウントを作成し、支持や批判を投稿する行為は「なりすまし」と呼ばれ、刑事罰の対象になります。アカウントの信頼性を確認するには、公式マークや発信元の履歴を見ることが大切です。万一見つけた場合は、選挙管理委員会やプラットフォームに報告しましょう。
ハッシュタグや拡散依頼の落とし穴
ハッシュタグ(例:「#○○候補応援」)を使って広める行為も、特定候補の当選を目的とすれば選挙運動とみなされます。一般有権者が自主的に行っても違反になる可能性があるため、慎重に判断が必要です。単なる政治的意見表明と混同しないよう注意しましょう。
DM機能・メッセンジャー機能の扱い
個人宛てに投票を呼びかけるメッセージを送ることは、基本的に禁止されています。特にLINEやXのDM機能を使った選挙運動は、メールと同じ扱いになり、候補者や政党以外は送信できません。友人間でも「○○に投票してね」と送るのは控えましょう。
画像・動画の著作権・肖像権と二次利用の注意
他人の写真や映像を無断で使用して選挙関連の投稿を行うと、著作権や肖像権の侵害に当たります。さらに、テレビ番組や新聞記事の画像を切り取って使うのも避けるべきです。候補者や支援者自身が撮影した素材を用い、出典を明記するのが安全です。
・誹謗中傷や虚偽情報の拡散は禁止
・なりすましアカウントの作成・拡散は刑事罰の対象
・ハッシュタグでの応援投稿も選挙運動と判断される場合あり
・DMやメッセージ機能による投票呼びかけは禁止
・画像や動画の使用は著作権・肖像権に配慮する
具体例:例えば、X上で「#○○候補を落選させよう」というタグを使って投稿を拡散した場合、公職選挙法の「落選運動」にあたる可能性があります。タグを付けるだけでも違反行為と判断されることがあるため注意しましょう。
- SNSの投稿も選挙運動に該当し得る
- 虚偽情報やなりすましは刑事罰対象
- ハッシュタグやDMの使用にも注意が必要
- 他人の画像・動画利用は許可を得る
- 安全な発信には一次情報の確認が欠かせない
メール・メッセージ配信での禁止事項
次に、メールやチャットツールなど「メッセージ配信」に関する禁止事項を確認します。ネット選挙運動では、候補者や政党のみが選挙運動目的のメール送信を認められています。一般の有権者が同様の行為を行うと、たとえ善意でも違法となる場合があります。
送信できる主体は誰か(候補者・政党の限定)
公職選挙法第142条の3により、選挙運動メールを送信できるのは候補者本人と政党などの政治団体に限られています。友人や支持者が自主的に同じ内容を転送することは認められていません。送信の範囲を誤ると、違反とみなされ罰則を受ける可能性があります。
一般有権者の転送禁止と例外の理解
受け取った選挙運動メールをそのまま別の人に転送するのも禁止されています。例外は、候補者自身が公式に発信したものをSNSで「共有」する場合のみ。これは「公表済み情報の再掲」として扱われるため、転送とは区別されます。ただし、加工や改変を加えると違法になることがあります。
LINE・グループDM・チャットツールのグレーゾーン
LINEやFacebookメッセンジャーなどは、メールと類似の機能を持つため、同様に候補者・政党以外の送信は禁止です。グループ内での「投票お願い」メッセージも違法となる可能性があります。家族や友人間でも、選挙運動目的の発言は控えましょう。
SMS・迷惑メール規制とオプトアウト
SMSを使った選挙運動も基本的に禁止です。さらに、メール配信を受け取る側には「拒否権(オプトアウト)」が認められています。受信を拒否した人に繰り返し送信する行為は、迷惑メール防止法違反にもつながります。
名簿・個人情報の取り扱いと適法範囲
メールアドレスや電話番号を用いた名簿作成には、個人情報保護法も関わります。選挙目的で第三者の連絡先を利用することはできません。必ず本人の同意を得たうえで使用することが原則です。
| 手段 | 許可される主体 | 禁止される行為 |
|---|---|---|
| 電子メール | 候補者・政党 | 一般人の送信・転送 |
| LINE・DM | 候補者・政党 | グループでの投票呼びかけ |
| SMS | 不可 | 一斉送信・勧誘 |
| メッセンジャー | 候補者・政党 | 転送・改変投稿 |
ミニQ&A:
Q1:候補者が発信したメールを家族に見せるのは違法ですか?
A1:閲覧させるだけなら問題ありません。ただし、内容を転送したりSNSで再投稿するのはNGです。
Q2:LINEグループ内で「○○さんを応援しよう」と言うのは?
A2:選挙運動とみなされる場合があり、候補者や政党以外が発言すると違反の可能性があります。
- メール送信は候補者・政党に限定されている
- 一般有権者の転送・再送は禁止
- LINEやDMでも投票呼びかけはNG
- 迷惑メールや個人情報の扱いにも注意が必要
- 例外規定を誤解しないように確認する
ウェブサイト・広告・表示義務でのNG
ネット選挙運動では、ウェブサイトや広告の扱いにも明確なルールがあります。情報発信を行う際には、責任の所在を示す「連絡先表示」や「管理者名」の明記が義務づけられています。違反すると、発信者が誰か分からない「匿名運動」とみなされ、罰則の対象となる場合があります。
連絡先・責任者表示の必須項目と書き方
候補者や政党がウェブサイトやブログ、SNSを通じて選挙運動を行う場合、ページ内に「発行責任者名・住所・連絡先」を明示する必要があります。これにより、誰が発信しているのかを明確にし、虚偽情報の拡散を防止します。特に、個人がボランティアとして支援する場合も、本人名義であることを明示しましょう。
投票日当日のサイト更新・予約投稿の落とし穴
投票日当日は、ブログやSNS、動画チャンネルなどすべての選挙関連更新が禁止です。予約投稿機能を使って自動的に更新される場合も違反と見なされるおそれがあります。投稿スケジュールを事前に確認し、投票日前に公開済みの内容も修正を加えないよう注意が必要です。
有料ネット広告の可否(政党のみの原則)

選挙運動を目的とした有料広告は、政党など特定の団体にのみ認められています。候補者個人や一般有権者が自費で広告を出すことはできません。SNS広告や検索エンジン広告も同様です。違反すると「不正広告」として処罰対象になることがあります。
ビラ・ポスターの画像公開と印刷配布の注意
ネット上に選挙用ビラやポスターの画像を掲載することは認められていますが、それを印刷して配布するのは違法です。また、印刷物の枚数や掲示方法にも制限があります。画像を扱う際には「デジタル公開」と「物理的配布」の区別を明確にしましょう。
届け出・表示ルールが求められるケース
政党や候補者は、インターネットを使って選挙運動を行う際、選挙管理委員会への届け出は不要ですが、サイトの管理者や連絡先の表示は義務です。特定のウェブサービスで政治広告を配信する場合は、事前にプラットフォームの規約に従う必要があります。
・サイトやSNSで選挙運動する際は責任者名の記載が必要
・投票日当日の更新・予約投稿は禁止
・有料広告は政党のみ可能
・画像公開と印刷配布の違いを理解
・届け出不要でも表示義務は必須
具体例:候補者が自分のブログで選挙活動を行う際、「発行責任者:○○太郎(住所・電話番号)」を明記せずに投稿を続けた場合、匿名運動と見なされ罰則の対象になる可能性があります。
- 責任者表示の明記は必須
- 当日更新・予約投稿は避ける
- 有料広告は政党のみ利用可能
- 画像の印刷配布は禁止
- 運用ルールを事前に確認することが重要
当事者別の注意点:候補者・政党・一般有権者・未成年
次に、立場ごとに注意すべきポイントを見ていきます。選挙運動のルールは一律ではなく、候補者・政党・一般有権者・未成年者で異なる制限が設けられています。それぞれの立場に応じた行動を心がけることが大切です。
候補者がやりがちなミスと未然防止
候補者自身がSNSを更新する際、投稿のタイミングや内容を誤るケースがよく見られます。たとえば、投票日当日に感謝のメッセージを投稿しただけでも「選挙運動」と解釈されることがあります。スタッフと投稿スケジュールを共有し、事前に停止設定を行っておくと安全です。
政党の広告運用で守るべきライン
政党がネット広告を出す場合も、内容が誤解を招く表現にならないよう注意が必要です。政策の比較や実績紹介は問題ありませんが、特定候補者への直接的な支持を促す表現は避けるべきです。広告の透明性を確保することで信頼性を高めることができます。
一般有権者が避けるべき拡散・呼びかけ
有権者が候補者の投稿をリツイートやシェアする行為も、内容によっては選挙運動に当たることがあります。特に「投票を呼びかける意図」が明確な場合は違反となる可能性が高いため、判断に迷うときは「情報の共有」に留めるのが無難です。
18歳未満・在外有権者の制限事項
18歳未満の者は選挙運動を行うことができません。SNSの「いいね」やコメントでも、内容によっては選挙運動とみなされることがあります。また、海外在住の有権者も国内の選挙に関する運動をオンラインで行うことは制限されます。
ボランティア・スタッフの行動ガイド
候補者を支援するボランティアや事務所スタッフも、投稿内容やタイミングを誤ると違反となる場合があります。候補者本人の承認を得た公式アカウントからのみ情報を発信し、個人のSNSでの自由投稿は避けるようにしましょう。
| 立場 | 注意すべき点 | 具体例 |
|---|---|---|
| 候補者 | 投票日当日の更新禁止 | 感謝投稿でも運動扱い |
| 政党 | 有料広告内容の透明性 | 誤解を招く訴えは禁止 |
| 一般有権者 | リツイート・シェアの扱い | 投票呼びかけ投稿はNG |
| 18歳未満 | 選挙運動の全面禁止 | 応援コメントも違反の恐れ |
| ボランティア | 個人SNSでの投稿禁止 | 公式経由の発信に限定 |
ミニQ&A:
Q1:候補者の投稿を「いいね」するのは違反ですか?
A1:単なる評価の意思表示であれば違反になりませんが、投票を促す意図がある場合は違法とされることがあります。
Q2:政党の広告を一般人がシェアするのはOK?
A2:内容が選挙運動を目的としない政策紹介であれば問題ありませんが、候補者名や投票を促す表現が含まれる場合は注意が必要です。
- 立場によってルールが異なる
- 候補者は当日投稿を避ける
- 政党は広告の内容と透明性を確保
- 一般人の拡散も選挙運動に該当し得る
- 18歳未満・在外者は選挙運動禁止
事例と罰則・トラブル対応の実務
最後に、ネット選挙運動で実際に起こった違反事例や、トラブルが発生した際の対応方法を見ていきましょう。選挙に関する法律違反は、意図せず起こしてしまうケースも多く、早期に正しい対応を取ることが重要です。ここでは、代表的な事例と対処法を整理します。
代表的な違反事例と該当条文の整理
過去には、SNSでの誹謗中傷や投票呼びかけ投稿が問題となったケースが複数あります。たとえば、ある地方選挙では一般有権者が「○○候補に投票を」とSNSに投稿し、公職選挙法第142条違反とされました。また、候補者本人が投票日当日にブログを更新してしまい、警告を受けた事例もあります。
名誉毀損・業務妨害との関係とリスク
ネット上の誹謗中傷は、公職選挙法だけでなく刑法上の名誉毀損罪や業務妨害罪にも関わります。虚偽の情報を投稿した場合、刑事罰だけでなく民事上の損害賠償請求を受けることもあります。投稿前に「根拠はあるか」「事実と異ならないか」を確認する習慣が大切です。
通報・削除依頼・証拠保存の手順
違反や誹謗中傷を発見した場合は、まずスクリーンショットなどで証拠を保存します。その上で、各SNSの通報機能を利用し、必要に応じて警察や選挙管理委員会へ相談します。投稿の削除を求める場合は、プラットフォームのガイドラインに沿った手続きが必要です。
違反の疑いが生じた際の初動対応
自分自身が誤って違反投稿をしてしまった場合は、速やかに削除し、経緯を明確にしておくことが重要です。悪質でなければ警告で済むこともありますが、放置すると重大な処分に発展することがあります。誤解を避けるために、公式な発信経路を一本化しておくと安心です。
デマ対策と一次情報によるファクトチェック
ネット選挙ではデマ情報が拡散しやすく、選挙結果に影響を与えることもあります。信頼できる情報源(総務省、選挙管理委員会、政党の公式サイトなど)を確認し、出典を明示することで誤情報を防げます。受け取る側も、感情的に反応せず、情報の真偽を冷静に確かめる姿勢が大切です。
・違反投稿を見つけたら証拠を保存
・名誉毀損や業務妨害にも注意
・削除依頼は公式ルートで行う
・誤って投稿した場合は速やかに削除
・情報発信前に一次情報で確認する
具体例:2023年の地方選挙では、候補者に関する虚偽の噂をSNS上で拡散した一般ユーザーが、名誉毀損容疑で書類送検されました。投稿者は「選挙運動のつもりではなかった」と説明しましたが、結果的に刑事事件に発展しました。このように、軽い気持ちの投稿でも法的責任を問われる可能性があります。
- SNS投稿の責任は投稿者自身にある
- 誹謗中傷・虚偽情報は刑事罰対象
- トラブル時は証拠保存と通報を優先
- 削除対応は迅速かつ公式ルートで行う
- 信頼できる一次情報を常に確認する
まとめ
インターネットを利用した選挙運動は、手軽で多くの人に情報を届けられる一方で、公職選挙法の制約を理解していないと違反になるおそれがあります。特に、SNS投稿やメッセージ送信、当日の更新などは、知らずに行ってしまうケースが少なくありません。
やってはいけない行為の多くは「公平な選挙を守るため」に設けられたルールです。候補者だけでなく、有権者やボランティアも同様に注意する必要があります。発信前には「この投稿は誰の利益につながるか」「投票を促す内容ではないか」を意識することが重要です。
正しい知識を持てば、ネット選挙運動は政治参加を広げる有効な手段になります。ルールを守りながら、健全で透明な情報発信を心がけましょう。