選挙の時期になると、SNS上でも候補者の発言や政策へのコメントが増えます。しかし、選挙期間中の投稿には法律で定められたルールがあり、知らずに違反してしまうおそれもあります。
例えば「投票を呼びかける投稿」や「候補者の投稿を拡散する行為」は、時期や方法によっては公職選挙法に触れることがあります。特に一般の有権者と候補者・政党では、できることの範囲が異なるため注意が必要です。
この記事では、総務省など公的機関の情報をもとに、選挙期間中にSNSで何が許され、何が禁止されているのかをわかりやすく整理します。普段通りの投稿が思わぬトラブルにつながらないよう、正しい知識を身につけておきましょう。
選挙期間中のSNSに関するルール(全体像と基本)
選挙期間中にSNSで発信する場合、公職選挙法という法律に基づく一定のルールが存在します。これは候補者だけでなく、一般の有権者にも適用されるものです。まずは、全体の仕組みと基本的な考え方を整理しておきましょう。
選挙期間の定義と「選挙運動/政治活動」の違い
選挙運動とは「特定の候補者の当選を目的として行う活動」を指します。一方で、政治活動は政策や意見の表明を目的とする一般的な行動で、期間に制限はありません。つまり、選挙運動が許されるのは「告示日(公示日)」から「投票日の前日」までと法律で定められています。
この違いを理解しないまま投稿すると、無意識に選挙運動とみなされるケースがあります。特に候補者名や政党名を明示して「応援します」「投票しましょう」といった表現を使うと、選挙運動と判断される可能性が高まります。
SNSでできること・できないことを一望する
インターネット選挙運動が解禁された2013年以降、SNS上での選挙関連投稿が可能になりました。ただし、すべて自由というわけではありません。候補者や政党は公式アカウントでの発信が認められていますが、一般有権者には禁止されている行為もあります。
例えば、候補者の代わりに「○○さんをよろしく」と投稿する行為や、メールを使った呼びかけは制限対象です。一方で、自分の意見として政策への感想を述べたり、公式発表をシェアすることは問題ありません。
年齢・国籍などの制限:18歳未満や外国人の扱い
18歳未満の人は、SNS上であっても選挙運動を行うことが禁止されています。これは投稿やリツイートも含まれるため、軽い応援メッセージでも注意が必要です。一方で、外国籍の人については、公職選挙法上「選挙運動をしてもよい」と明示されており、国内在住の外国人が政治的な意見をSNSで表明すること自体は制限されていません。
ただし、選挙権を持たない立場であっても、虚偽情報の拡散や誹謗中傷を行えば処罰の対象となるため、言葉の選び方には十分な配慮が必要です。
違反時の主な罰則と責任の所在
公職選挙法に違反した場合、罰金や禁錮刑が科される可能性があります。特に「なりすまし」や「誹謗中傷」に該当する行為は重く処罰される傾向にあります。また、投稿した本人だけでなく、拡散や運用を手伝ったスタッフなどにも責任が及ぶことがあるため注意しましょう。
つまり、SNS上での発信は“軽い発言”でも公的な影響力を持つ可能性があるという意識が欠かせません。選挙に関する情報を扱う場合は、一次情報の確認を徹底しましょう。
まず確認したい一次情報(公的資料)の見方
総務省の「インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁」ページや、各自治体の選挙管理委員会が発行するガイドブックには、具体的な可否事例が掲載されています。公式PDFやQ&A形式の資料を確認すれば、SNS投稿に関する疑問の多くは解消できます。
特に総務省のサイトでは、選挙運動に関する用語や違反時の罰則、通報窓口まで明記されています。信頼できる一次資料を活用することで、誤った情報に惑わされずに済むでしょう。
・SNS投稿は「選挙運動」か「政治活動」かをまず判断
・候補者名を出す場合は「投票呼びかけ」に注意
・18歳未満は選挙運動禁止
・公的資料(総務省・選管)を必ず確認
具体例: 例えば「○○候補の政策が素晴らしい。ぜひ投票してほしい」と投稿すると選挙運動に該当しますが、「○○候補の政策を読んで考えさせられた」と意見を述べるだけなら問題ありません。この違いが理解の第一歩です。
- 選挙運動と政治活動の違いを理解する
- 一般有権者にもルールがある
- 18歳未満はSNSでも選挙運動禁止
- 違反には罰則がある
- 一次情報を確認して誤情報を防ぐ
いつからいつまで?期間別のOK/NG
選挙期間中のSNS投稿で最も誤解されやすいのが「時期」に関するルールです。選挙運動ができるのは、告示日(国政選挙では公示日)から投票日の前日まで。ここを境に、許される投稿と禁止される投稿が明確に分かれます。
告示・公示前に注意すべき投稿の線引き
告示前の期間は、正式な選挙運動がまだ認められていません。したがって、特定候補者を応援する投稿や投票を促す呼びかけはできません。ただし、政策への意見表明や、政治に関する一般的な投稿は問題ありません。
例えば「○○候補を応援します」と書くと選挙運動に該当しますが、「○○氏の発言に共感した」と書く場合は政治的意見にとどまり、法律上の問題はありません。このように、意図や表現の違いで線が変わることを理解しておく必要があります。
告示(公示)後〜投票日前日の運用ルール
この期間に入ると、候補者や政党はSNSで選挙運動を行うことができます。一方、一般有権者ができるのは「候補者の投稿へのコメント」や「政策紹介のシェア」までで、投票依頼は禁止です。
また、電子メールによる投票呼びかけは、候補者と政党以外は禁止されています。これはスパム行為や誤情報の拡散を防ぐための措置であり、SNSとは異なる扱いになります。
投票日当日の禁止事項とよくある誤解
投票日当日は、すべての選挙運動が禁止されます。SNSで「投票に行こう」「○○候補を応援しています」と投稿するのはNGです。たとえ意図がなかったとしても、「投票呼びかけ」と判断される可能性があります。
ただし、「投票に行ってきた」「選挙管理委員会の情報を共有する」といった中立的な投稿は問題ありません。この違いを理解しておくことが重要です。
当日更新の可否:ホームページやSNSの扱い
投票日当日は、候補者・政党がホームページやSNSを更新することも禁止されています。ただし、過去に投稿した内容を削除したり、閲覧できる状態のままにすることは認められています。新しい投稿・広告配信・ライブ配信は違反にあたる可能性があります。
一方で、選挙とは関係のない内容を投稿する場合は問題ないとされていますが、誤解を避けるため、当日は政治に関する投稿を控えるのが無難です。
グレーになりやすいケースの判断材料
特定候補を連想させる表現やハッシュタグ(例:「#変えよう未来」「#○○支持」など)は、文脈によっては選挙運動と見なされます。選挙管理委員会も「一般論として慎重な運用を」と注意を呼びかけています。
つまり、投稿の意図や受け取られ方が重要です。判断に迷う場合は、選挙管理委員会のQ&Aや総務省の事例集を確認するか、専門家に相談すると安心です。
・告示前:選挙運動は一切禁止
・告示後〜前日:候補者・政党のみ選挙運動可
・投票日当日:投稿・更新すべて禁止
・判断に迷うときは「公的資料を確認」
具体例: たとえば、投票日前日の夜に「明日は○○候補に投票します」と投稿するのは違反ですが、「明日は選挙、投票に行こう」とだけ書けば問題ありません。表現の差が結果を左右します。
- 選挙運動ができるのは告示日から前日まで
- 一般人は期間中の投票呼びかけ禁止
- 当日はSNS更新も選挙関連は禁止
- 誤解を招く表現にも注意
- 不安なときは公的ガイドを確認
手段別ルール:X・Instagram・LINE・YouTube・メール
SNSといっても、それぞれの特徴によって許される行為や注意点は異なります。ここでは代表的な5つの手段を取り上げ、それぞれの運用ルールを整理します。
X(旧Twitter)でのリツイート・引用・スペース配信
Xでは候補者や政党の投稿をリツイートしたり、引用投稿することができます。ただし、その内容が「投票を依頼する」ものであれば、一般の有権者による拡散は選挙運動とみなされる可能性があります。つまり、賛同の意を示すだけでも、文面によっては違反になることがあるのです。
また、音声配信機能「スペース」を利用して候補者や政策を応援する発言をする場合も注意が必要です。特定候補への支持を呼びかける内容は、選挙運動と判断されます。
Instagram:ストーリーズ・リールの注意点
Instagramでは、写真や動画を通じた発信が中心です。投稿自体は問題ありませんが、「投票依頼」「支持呼びかけ」などを含む内容は違反となります。特にストーリーズやリールは消える投稿のため、気軽に発信しがちですが、法律上の扱いは通常の投稿と変わりません。
また、タグ付けやハッシュタグの使用にも注意が必要です。「#○○候補」「#○○党応援」などのタグは明確な選挙運動と見なされる可能性があります。
LINE:個別メッセージやグループ投稿の扱い
LINEでの選挙運動は、特に厳しく制限されています。候補者や政党を除き、一般の有権者がLINEで投票依頼のメッセージを送ることは禁止されています。グループLINEでも同様で、「友人に送っただけ」でも違反になる恐れがあります。
一方で、政策紹介の記事URLを共有したり、公的機関が発信する情報を転送することは問題ありません。つまり、内容が「依頼」ではなく「情報提供」であれば許されるのです。
YouTube・ライブ配信・投げ銭(スパチャ)の論点
候補者や政党はYouTubeを使った動画配信で政策を訴えることができますが、一般の人がライブ配信中に「投票お願いします」などとコメントすると違反になる可能性があります。さらに、スーパーチャット(投げ銭)機能を使うと「金銭提供」と解釈される場合があり、非常に慎重な対応が求められます。
また、動画の概要欄に「支援お願いします」「○○候補に投票を」と記載することも選挙運動とみなされます。動画発信は影響力が大きいため、投稿前に十分な確認が必要です。
メールは候補者・政党のみ可:例外と実務の注意
公職選挙法では、電子メールを使った選挙運動を「候補者と政党に限定」しています。つまり、一般有権者が友人や知人に投票依頼メールを送ると違反になります。メール転送も禁止されているため、善意でも慎重に対応しましょう。
一方で、候補者が登録者に送るメールマガジンなどは認められています。ただし、受信拒否の手段を明示することが義務づけられています。法律の範囲内での情報発信が大切です。
・Xのリツイートは内容次第で違反
・Instagramのタグも要注意
・LINEの個別メッセージは禁止
・YouTubeの投げ銭は慎重に
・メールは候補者・政党のみ許可
具体例: たとえば友人に「○○候補をよろしく」とLINEを送るのは違反ですが、選挙管理委員会の投票案内リンクを共有するのは問題ありません。この違いを理解することがトラブル防止につながります。
- SNSごとにルールが異なる
- LINEやメールは特に制限が厳しい
- 動画・ライブ配信には慎重さが必要
- 投稿前に「投票依頼」になっていないか確認
- 疑問があれば選挙管理委員会に相談
有権者(一般の人)が気をつけるポイント
選挙期間中にSNSを使うのは候補者だけではありません。一般の有権者も意見を表明できますが、やり方を誤ると公職選挙法違反となることがあります。ここでは一般市民が特に注意すべきポイントを解説します。
シェア・転送・DMはどこまで許されるか
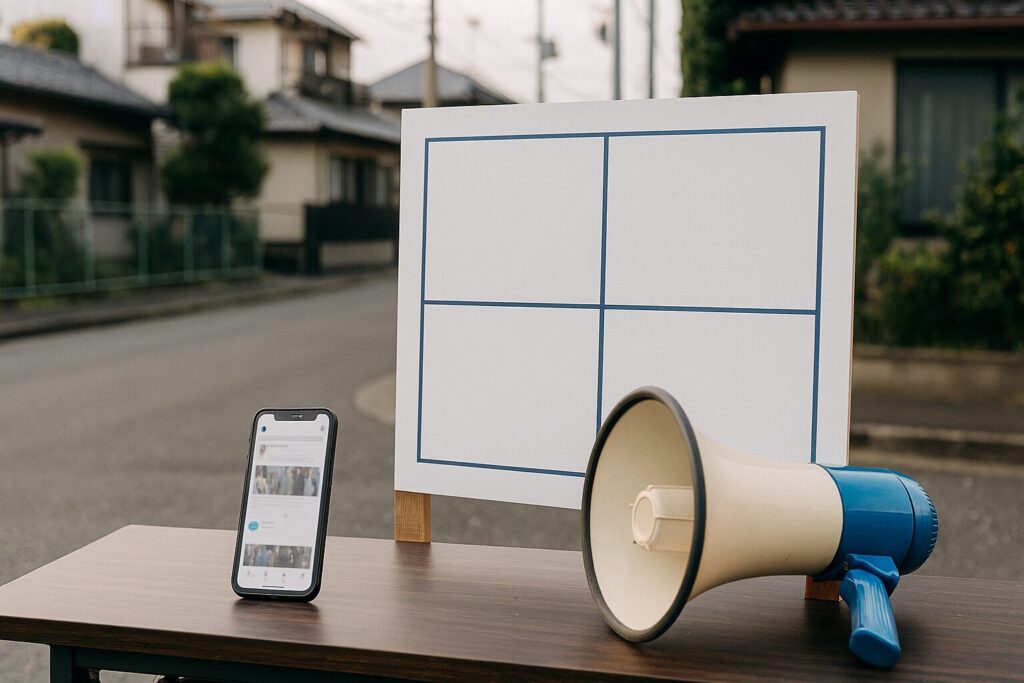
一般人が候補者の投稿をシェアすること自体は可能ですが、その際に「投票依頼」と受け取られるコメントを加えると違反になる恐れがあります。また、DM(ダイレクトメッセージ)で特定の候補を勧める内容を送ることも禁止です。
つまり、拡散は「情報共有」にとどめることが大切です。SNSは双方向の特性があるため、意図せず選挙運動と見なされる場合がある点を理解しておきましょう。
なりすまし・誹謗中傷・虚偽拡散のリスク
候補者や政党になりすます行為、または誹謗中傷・虚偽の情報を投稿する行為は、刑事罰の対象になります。SNS上では拡散速度が速いため、一度投稿すると完全に削除するのが困難です。誤った情報を広めた場合、謝罪や訂正だけでは済まないこともあります。
このため、発信前に「事実かどうか」を確認することが最も重要です。感情的な投稿は避け、冷静な言葉で意見を述べるよう心がけましょう。
画像・ビラ・ポスターをSNSに載せるときの留意点
選挙期間中に街頭で配られるビラやポスターを撮影してSNSに投稿する場合は注意が必要です。特に候補者の名前や政党ロゴが明確に写っている画像を「応援目的」で拡散すると、選挙運動と見なされる場合があります。
一方で、報道的な目的や一般の記録として投稿する場合は問題ありません。投稿の意図と文脈によって判断が変わるため、説明文を慎重に書くことが大切です。
炎上・通報・削除依頼の手順と証拠保全
もしSNS投稿が問題視された場合、まず削除することが第一です。そのうえで、投稿内容や経緯をスクリーンショットで保存しておきましょう。これは、誤解や悪意ある通報に対抗するための重要な証拠となります。
また、各SNSには通報機能があります。不適切な投稿を見つけた場合は、冷静に通報手続きを行い、感情的な反論を避けることがトラブル防止につながります。
未成年者が投稿する場合の注意事項
18歳未満は選挙運動そのものが禁止されています。たとえ「応援しているだけ」といっても、選挙期間中に候補者名を出す投稿は控えるべきです。また、家族の投稿をリポストする場合も同様の扱いになるため注意しましょう。
学校の授業などで選挙を取り上げる際も、特定の候補や政党を支持する内容は避ける必要があります。教育現場でも政治的中立が求められるのです。
・投票依頼と受け取られる投稿はNG
・虚偽情報や誹謗中傷は重い処罰対象
・画像投稿も目的次第で違反になる
・未成年者は選挙運動禁止
・トラブル時は証拠を保全して対応
具体例: 例えば「○○候補のポスターを撮った!応援してます!」と投稿するのは選挙運動ですが、「街で見かけた選挙ポスター。いよいよ選挙ですね」と中立的に述べるのは問題ありません。意図を明確にすることがポイントです。
- シェアやDMも内容次第で違反になる
- 誹謗中傷やなりすましは刑罰対象
- 投稿前に意図と表現を確認
- 未成年者の投稿は特に注意
- トラブル時は冷静に対応し証拠を残す
候補者・陣営のSNS運用ルール
候補者や政党、支援者がSNSを利用して選挙活動を行う場合、法律上のルールと運用上の注意点が細かく定められています。特に、連絡先の明示や有料広告の扱いなど、一般有権者とは異なる義務も多く存在します。
連絡先表記義務と表記の実例
候補者や政党がSNS上で選挙運動を行う際には、投稿やプロフィール欄に「連絡先(住所・電話番号・責任者氏名など)」を明記する必要があります。これは、発信者を特定しやすくすることで、なりすましや誤情報の拡散を防ぐための仕組みです。
たとえば、「〇〇選挙事務所(東京都千代田区〜)」といった表記を添えることで、法的要件を満たすことができます。明記がない場合、形式上の違反となる可能性があります。
有料広告は原則「政党のみ」:適法な出稿条件
インターネット上の有料広告(リスティング広告やSNS広告など)は、政党のみが出稿可能とされています。候補者個人が費用を支払い、SNS上で広告を配信することは原則禁止です。例外的に政党の管理下で配信される場合を除き、個人広告は違法となる可能性があります。
このため、候補者は政党の広告運用方針に従い、統一されたガイドラインのもとで配信を行う必要があります。選挙ごとに定められる「広告出稿ルール」を確認することが大切です。
スタッフ運用・ガイドライン・権限管理
選挙期間中、複数のスタッフがアカウントを管理する場合は、運用ルールの共有が欠かせません。誤投稿や誤解を防ぐために、投稿前の確認フローを設けるのが基本です。また、ログイン権限の管理を怠ると、第三者による不正投稿のリスクが高まります。
投稿スケジュール、画像の承認手順、コメント対応など、すべてを文書化しておくことが望ましいでしょう。特に炎上対応時は迅速な判断が求められるため、権限範囲を明確にしておくことが重要です。
虚偽情報への初動対応と訂正の出し方
SNSでは、誤情報が瞬時に広がることがあります。候補者や政党が虚偽情報を発見した場合、削除要請や訂正投稿を速やかに行う必要があります。誤情報を放置すると、風評被害が拡大し、選挙全体への信頼を損ねるおそれがあります。
訂正を行う際は、感情的にならず事実のみを伝えることがポイントです。公的資料や公式発表を引用し、冷静に対応することで信頼性を高められます。
ログ保存・アーカイブ化で備える監査対応
選挙後に問題が指摘された場合に備えて、SNS投稿のログを保存しておくことが推奨されます。投稿履歴やコメントの記録を残すことで、万が一の際の証拠として活用できます。
また、クラウド上にアーカイブを作成しておくことで、監査や選挙管理委員会からの問い合わせにもスムーズに対応できます。透明性の確保は、信頼される候補者・政党の基本姿勢といえるでしょう。
・連絡先表記を忘れずに明記
・有料広告は政党のみ可
・スタッフ運用はガイドラインを共有
・誤情報には迅速・冷静に対応
・投稿ログを保存して透明性を確保
具体例: たとえば、候補者がSNS広告を自費で出稿した場合は違法となりますが、政党本部が一括で出稿し候補者の投稿を紹介する形であれば合法です。このように出稿主体が誰かで扱いが変わります。
- 候補者は連絡先の明示が義務
- 有料広告は政党限定
- スタッフ運用には管理体制が必須
- 誤情報は即訂正・記録保存
- 透明な発信で信頼性を高める
OK/NGを事例で判定
ここからは、実際にありがちなSNS投稿をもとに、どこまでが「OK」でどこからが「NG」なのかを事例で確認していきます。曖昧な表現や判断に迷う場面を理解することで、トラブルを防ぐことができます。
投票依頼と情報提供の線引き(文言比較)
「投票依頼」と「情報提供」は紙一重です。たとえば「○○候補に投票をお願いします」は明確な選挙運動でNG。一方、「○○候補の政策を紹介します」は情報提供として認められます。
文末の語尾や意図が判断のカギです。選挙管理委員会の指針でも「投票を依頼する表現を避けること」と明記されています。
投票日当日の投稿:呼びかけ・誘導の可否
投票日当日は「選挙運動」が一切禁止されます。「投票に行こう」「投票しました」といった投稿は一見問題なさそうですが、特定候補への誘導を含むと違反になります。
「#選挙行こう」「#投票済み」など一般的な呼びかけは許されていますが、文脈や画像によっては誤解されることもあります。できるだけ中立的な表現にとどめましょう。
外部サイト誘導・URL掲載・ハッシュタグ運動
候補者や政党の公式サイトへのリンクを貼ること自体は合法です。しかし、投票を依頼する文面と一緒にリンクを掲載すると選挙運動となります。また、ハッシュタグ運動(#○○支持など)も、組織的に行われると違法と判断されることがあります。
つまり、SNSでは「文脈と組み合わせ」で合法かどうかが決まるのです。リンクを貼る際は、紹介目的にとどめるよう意識しましょう。
キャンペーン・プレゼント企画の落とし穴
フォローやリポストで抽選プレゼントを行う「キャンペーン形式」の投稿は注意が必要です。選挙期間中にこれを行うと「利益誘導」とみなされるおそれがあり、買収行為として処罰対象になります。
SNSマーケティングの感覚で企画してしまうと違反になりかねません。キャンペーンやプレゼントは、選挙期間が終わってから実施するようにしましょう。
政見・落選運動の実例と注意点
選挙期間中に特定候補を批判する「落選運動」も、やり方によっては違法となります。事実に基づく批判や意見表明は認められていますが、誹謗中傷や虚偽情報を含む場合は処罰の対象です。
つまり、意見と中傷は違います。根拠に基づく批判は言論の自由の範囲内ですが、感情的・攻撃的な投稿は控えるべきです。
・「投票してください」はNG
・「政策を紹介します」はOK
・リンク掲載は文脈次第
・プレゼント企画は違反の恐れ
・根拠なき批判は処罰対象
具体例: 「○○候補の政策サイトはこちら(リンク)」はOKですが、「○○候補に清き一票を!詳細はこちら(リンク)」は違法となります。このように、同じリンクでも文脈で意味が変わります。
- 投稿の文脈が合法・違法を分ける
- 投票日当日は投稿しないのが安全
- キャンペーンは選挙後に実施
- 批判は事実に基づく範囲で行う
- SNSの自由と法のバランスを意識
最新動向と今後の見直し
インターネット選挙運動が解禁されてから10年以上が経ち、SNSを取り巻く環境は大きく変化しています。特に動画投稿やライブ配信の普及により、候補者と有権者の距離が一層近づきました。その一方で、誤情報や過激な発信のリスクも増しており、法制度の見直しが進められています。
ネット選挙解禁以降の変化と実務への影響
2013年の制度改正により、候補者・政党はSNSで選挙運動ができるようになりました。それ以降、XやInstagramを活用する候補者が増え、政治への関心を高める効果が見られました。一方で、一般有権者が誤って違反投稿を行うケースもあり、啓発活動の重要性が増しています。
この変化により、選挙管理委員会もSNSのモニタリング体制を強化しています。投稿の拡散力が大きいほど、責任も伴う時代になったといえるでしょう。
投げ銭・収益化・動画広告をめぐる最新論点
最近では、YouTubeなどの動画配信プラットフォームで「投げ銭(スーパーチャット)」を受け取るケースが議論を呼んでいます。支援者が候補者に金銭を送る行為は「寄付」にあたる可能性があり、現行法では慎重に扱う必要があります。
また、動画広告による訴えも一般化しましたが、配信元の透明性が課題です。誰が費用を負担したのか、どの地域で配信されたのかが明示されないと、公平性を欠くおそれがあります。
総務省・自治体の最新ガイドの更新傾向
総務省は毎年、インターネット選挙運動に関する「Q&A」や解説資料を更新しています。特に近年はSNS別の具体事例が追加されており、たとえば「ストーリーズ投稿」「リツイート」「ライブ配信」などの可否が細かく整理されています。
自治体によっては独自のチェックリストを公開しているところもあります。最新情報を確認することで、ルールの変化に柔軟に対応できるでしょう。
次回選挙までに整える社内運用とチェックリスト
候補者や支援団体は、次の選挙に備えてSNS運用ルールを再点検する必要があります。運用マニュアルを整備し、スタッフの教育を行うことで、誤投稿や炎上を未然に防げます。
一般の有権者にとっても、政治的発言の自由を守るために法令を理解することは重要です。SNSを通じて政治に参加する際は、正確な情報と法的知識の両方を備えることが信頼される発信につながります。
読者向けダウンロード資料の活用方法
多くの自治体や総務省のサイトでは、インターネット選挙運動のガイドブックをPDFで公開しています。印刷しておくと、実際の投稿時に「これは大丈夫かな?」と迷ったときの判断材料になります。
公的資料は信頼できる一次情報です。SNS上で流れる断片的な情報よりも、根拠が明確で誤解を防ぎやすい点が大きな利点です。選挙のたびに最新版を確認する習慣をつけましょう。
・SNS選挙は「双方向」時代へ進化
・投げ銭や広告収益の扱いが新たな課題
・総務省ガイドは毎年更新されている
・透明性と法令順守が今後のカギ
・有権者も知識を持って安全に発信
具体例: 例えば、地方自治体の選挙管理委員会が配布する「インターネット選挙運動Q&A集」には、SNS別にOK・NG事例が一覧化されています。こうした資料を参照すれば、迷ったときにも安心して投稿を判断できます。
- ネット選挙の自由化は進む一方で責任も増加
- 動画配信や投げ銭は新たな法的論点
- 最新ガイドを毎年確認することが重要
- 候補者も有権者もSNSルールの理解が不可欠
- 信頼できる一次情報を活用して発信の質を高めよう
まとめ
選挙期間中にSNSで発信する際は、「いつ」「誰が」「どのような目的で」投稿するかを明確にすることが大切です。特定候補への投票依頼や、誤解を招く表現は公職選挙法違反となるおそれがあります。一方で、事実に基づいた情報共有や意見表明は、民主主義を支える重要な行動でもあります。
つまり、SNSを使う際は「自由」と「ルール」の両立が求められます。候補者や政党だけでなく、有権者一人ひとりが正しい知識を持つことで、健全な選挙文化を守ることができるのです。次回の選挙に向けて、自分の投稿を見直し、安全で誠実な発信を心がけましょう。
公的資料や総務省・自治体のガイドラインを定期的に確認すれば、法律の変化にも対応できます。SNSの使い方ひとつで、政治参加の形はより良い方向へ進めるはずです。



